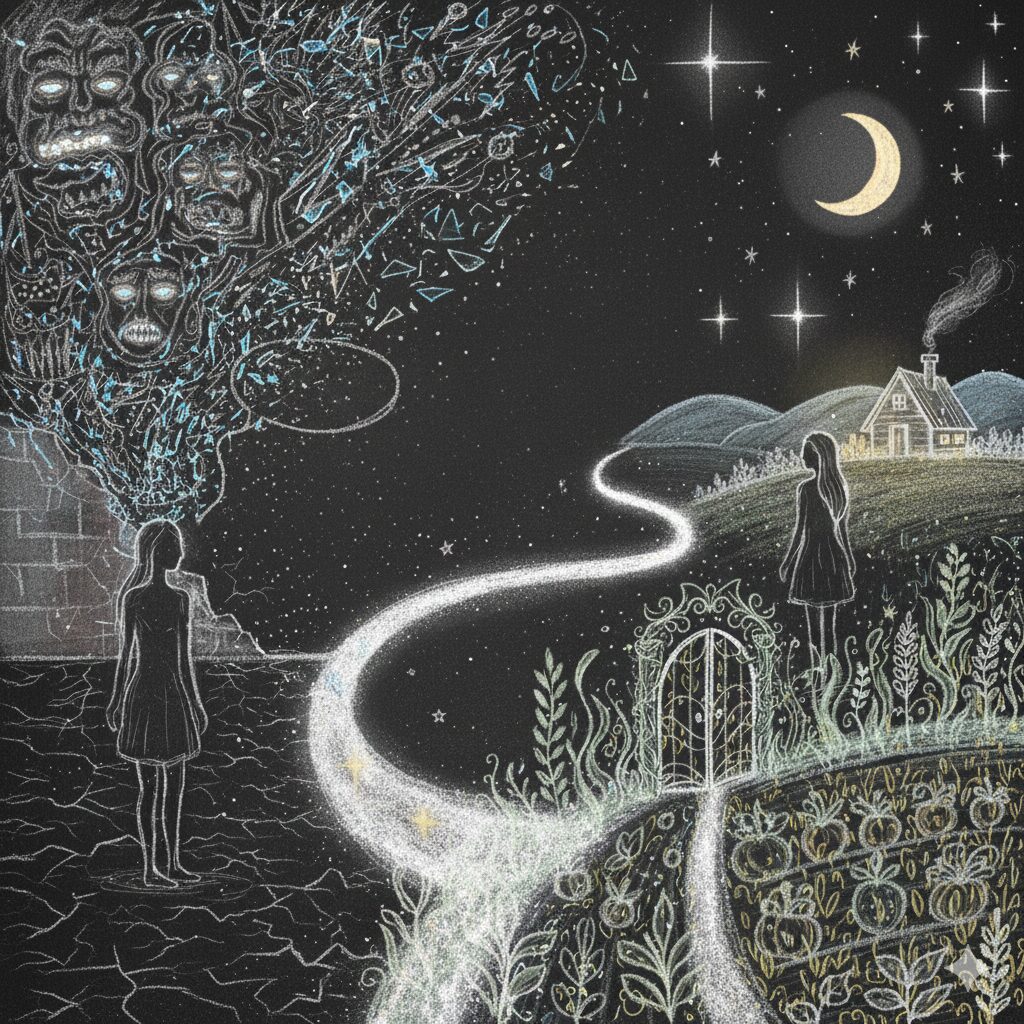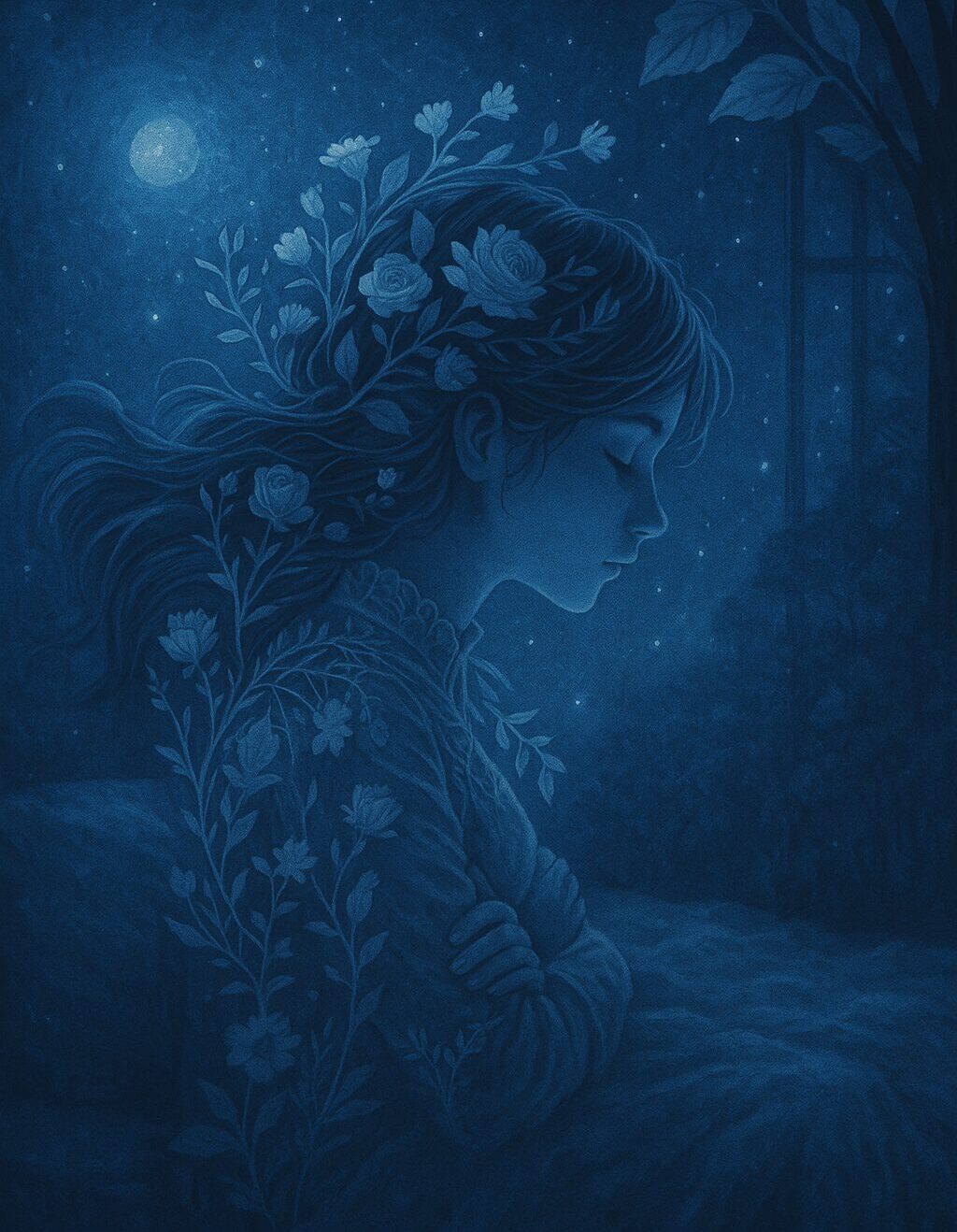HSPと動物 ― 孤独な子猫との日々が教えてくれた共感の力

冬の寒さと敏感な心
ある冬の朝、駐車場で小さく丸まって震える子猫を見つけました。凍える体と、不安そうに見上げる瞳――その姿は、私の胸に深く刺さりました。
HSPの私は、周囲の反応や迷惑になる可能性をすぐに想像してしまいます。しかし、その孤独な小さな命を前に、「もし自分が同じ状況だったら」と自然に思いが湧き、手を差し伸べずにはいられませんでした。

共感が生む行動
私は犬用のケージを駐車場に置き、毛布を敷きました。
子猫は最初、警戒心から「シャーッ」と威嚇しましたが、それでも少しずつ安心してケージで眠るようになりました。
毎朝、仕事に行く前にキャットフードを置き、食べ終わるまでそばで見守る日々が続きました。
捕まえたトカゲの死骸を食べようとしたときには、思わず手を出して止めようとして引っかかれ、血が出ることもありました。
夜になると、子猫は庭にやってきて窓を叩き、ニャーニャーと鳴きながら家に入りたそうにすることもありました。
ウチのワンコが庭で遊んだあと家に入ると、自分も入りたくてついてくるのに入れてもらえない。そうすると悲しそうな表情を浮かべます。
その小さな表情や仕草ひとつひとつが、敏感な私の心に直接響き、自然に「助けたい」「安心させてあげたい」という行動につながっていきました。



生き物同士の安心感
子猫は人間には警戒心が強い一方で、家の犬にはすぐに懐きました。
犬と子猫の間に漂う安心感や信頼感は、HSPのように「相手の雰囲気や環境の微妙な差」に敏感な性質が生き物同士にも現れた瞬間のように感じられました。
さらに、ウチのワンコが愛用しているぬいぐるみをケージに入れると、大事そうに抱えて眠る姿がありました。その姿に、微細な感情のやり取りが確かに存在していることを感じました。


夏と命の危うさ、そして相互の癒し
夏が近づくと、猛暑やノミ・ダニの影響で子猫の毛があちこち抜け、体調も心配になる状態になりました。
見るたびに胸が締め付けられ、「なんとかしてあげたい」という思いが強くなります。
家の中に迎え入れる準備を整え、壁や家具に引っかかれても大丈夫なようシートを貼り、トイレを設置するなど工夫を重ねました。
そして、夏の猛暑が始まる前に、ついに子猫を家族として迎え入れることができました。名前は「マル」。
マルを救った感覚だけでなく、毎日の世話の中でマルからも癒しや安心をもらい、私自身もまた救われていることを実感しました。
敏感な心は、相手の小さな変化を察知するだけでなく、こうして互いの心を温め合う力にもなるのです。


HSPとしての学び
敏感さや共感力は、時に過剰な不安や心配を生む性質です。
しかし、マルとの日々から学んだのは、HSPの感受性は弱点だけではなく、命や心のつながりを守り、絆を育む力にもなるということです。
小さな変化や感情を感じ取り、それに応じて行動することが、日常に喜びや癒しをもたらすのだと知りました。

まとめ
この体験を通して改めて感じたのは、HSPの敏感さは決して弱点だけではないということです。小さな変化や他者の感情に気づきやすいからこそ、孤独な子猫の不安や恐怖を察知し、手を差し伸べる行動につながりました。
マルと過ごす日々は、救ったという一方通行の感覚ではなく、互いに癒し合う関係でもありました。敏感な心が、相手の安心感や信頼を感じ取り、互いの存在に喜びを見出す――そんな微細なつながりが、日常を豊かにしてくれます。
HSPとして生きる私たちは、過剰な不安や疲れに悩むこともありますが、それと同時に、他者や環境と深くつながる力を持っています。この体験は、感受性を生かすことで、小さな命を守り、絆を育み、互いに癒されることができるという学びを教えてくれました。
敏感さを恐れず、むしろその力を受け入れることで、日々の生活の中に喜びや安心を見つけることができる――それがHSPの強みでもあるのです。
HSP心理学と心の整え方
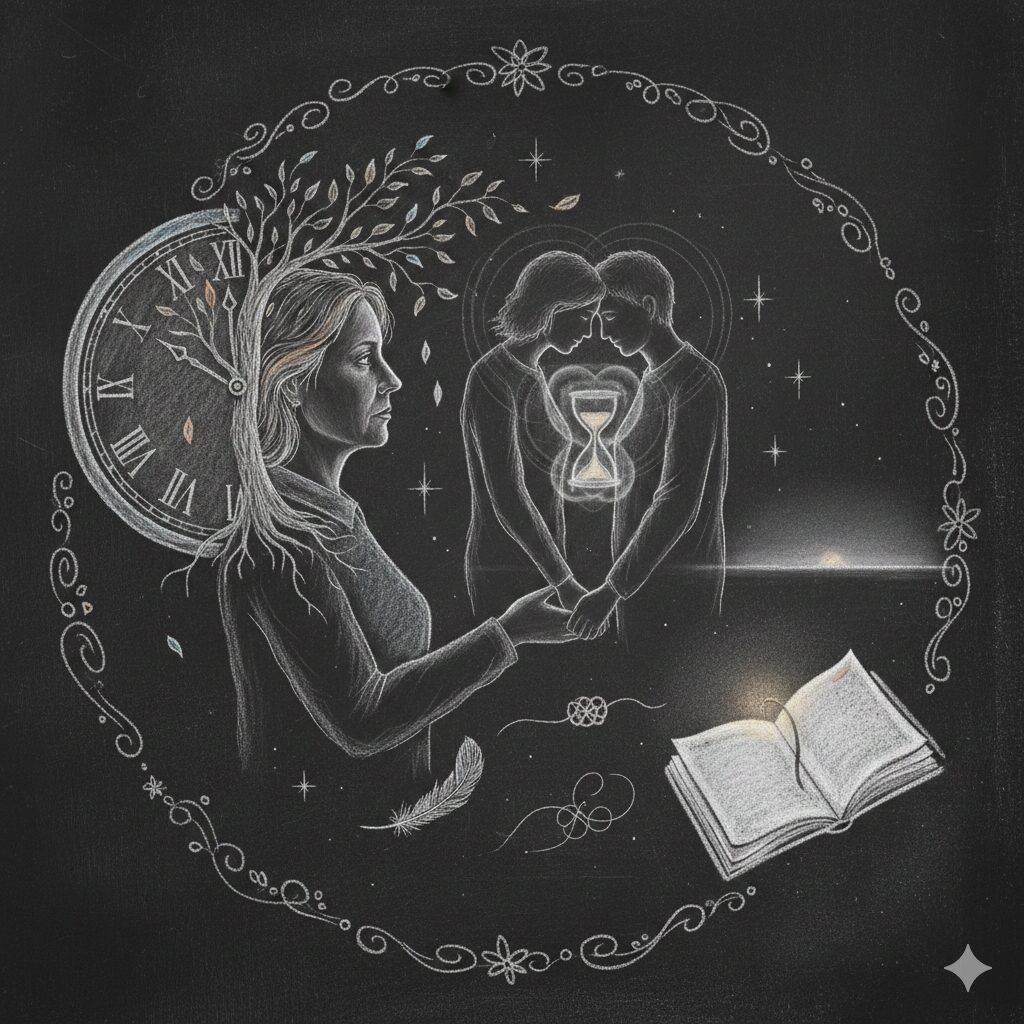
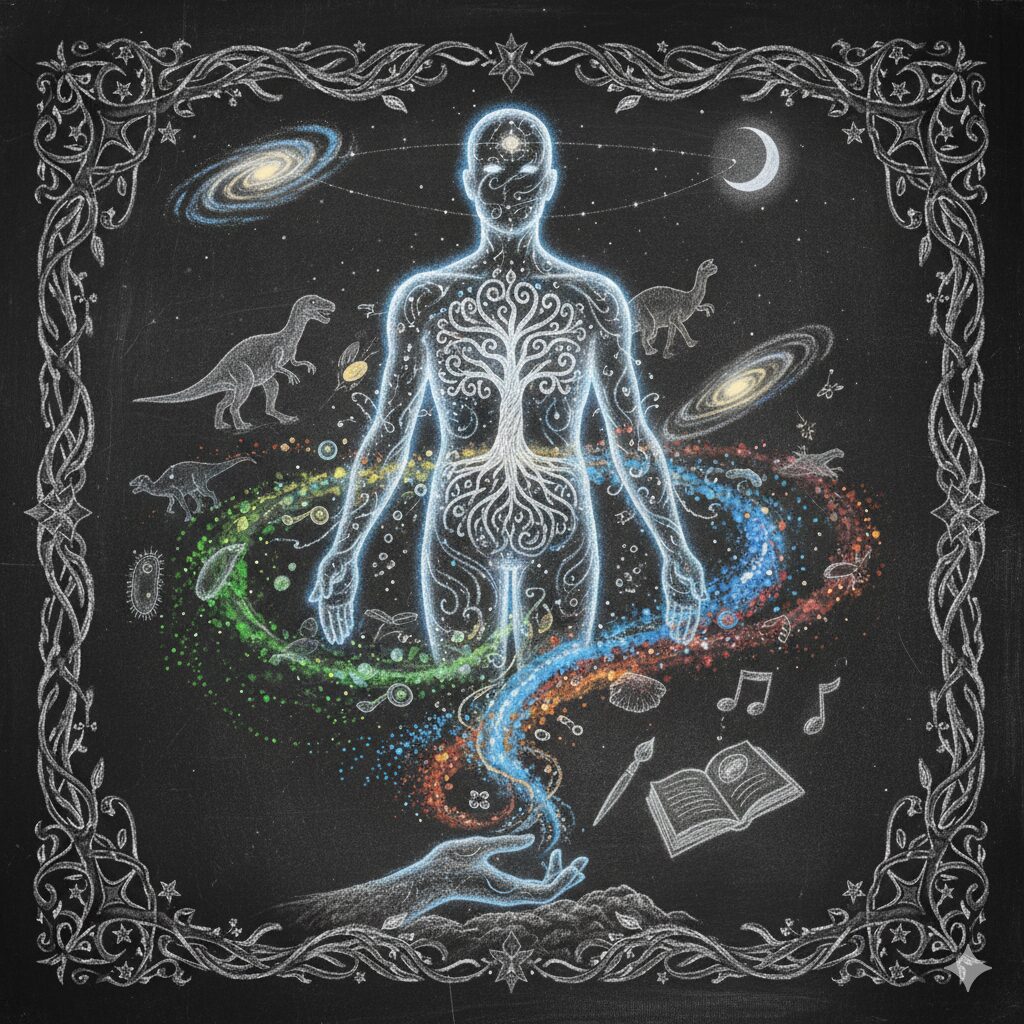

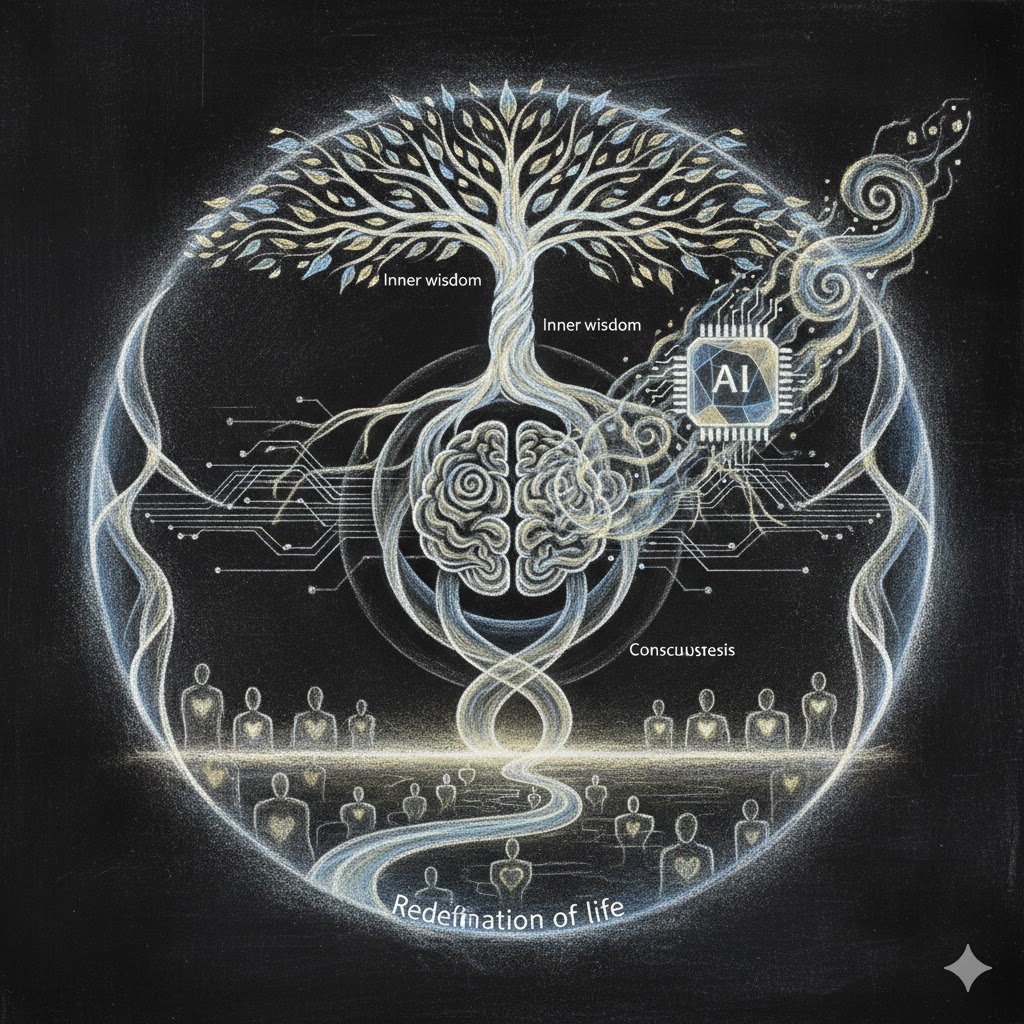
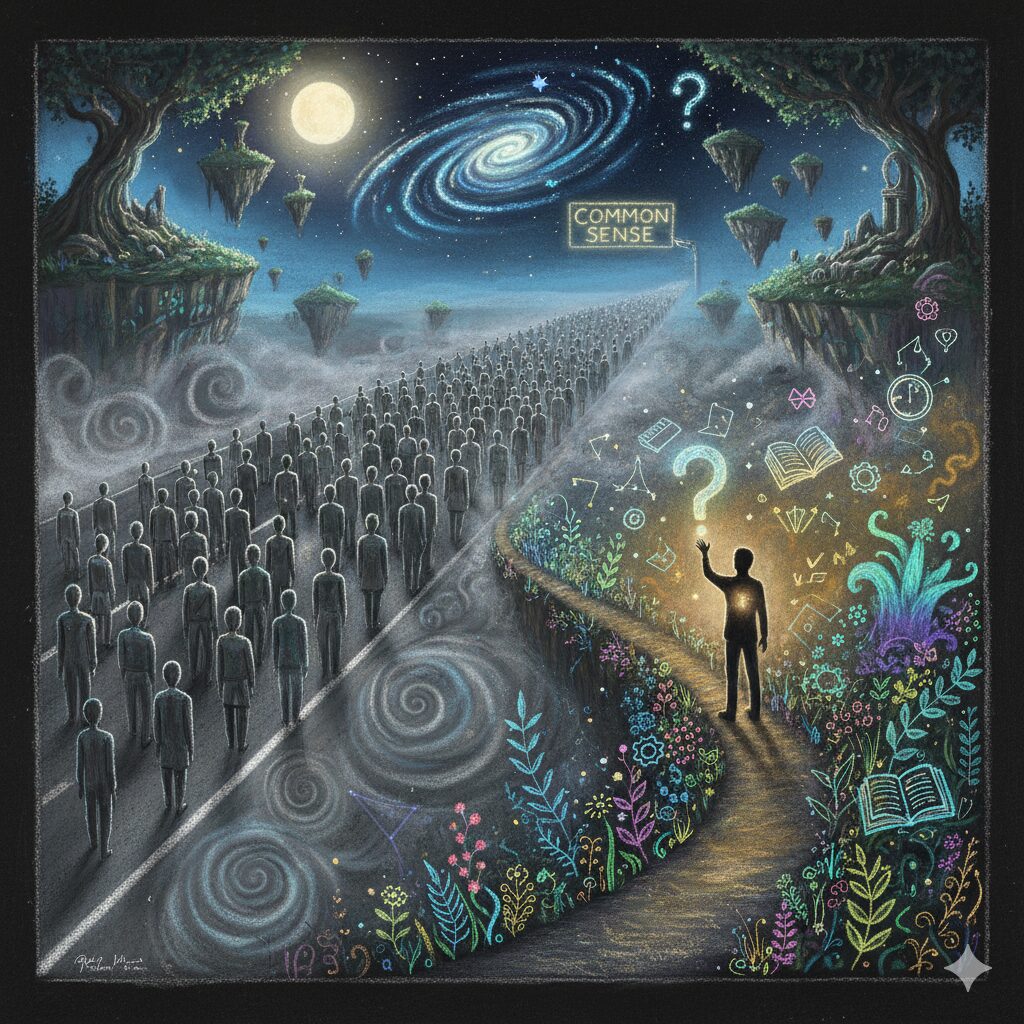

新着記事